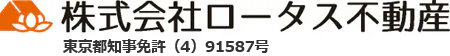中古住宅の売却費用
author:春日秀典
不動産売却を考えていますか?でも、かかる費用が気になりますよね。その中でも最大のものは仲介手数料です。これはいくらでしょうか?
そして、売却にはいくつかの必須経費があります。あなたの大切な資産を賢く売却するため、知っておくべき費用とは何でしょうか?
公開日: 更新日:
必須経費
売却に係る主な費用は仲介手数料です。買取での売却でかかる費用は「買取で売却するときの流れ・経費」をご覧ください。銀行費用の繰り上げ返済、抵当権抹消の費用などは、当社が受領する以外の費用です。各業者へお支払いください。
仲介手数料
売却費用のなかでもっとも大きな位置を占めるのが仲介手数料です。当社においては3%(税込み)を基本としています。
仲介手数料は成功報酬です。仮に売却活動を依頼しても、成約に至らなければ手数料は発生しません。広告宣伝費などは仲介手数料のなかに含まれています。お客様のたっての希望で特別な売却広告を依頼することもありますがふつうはそのようなことはないでしょう。
当社においては買取への売却は仲介手数料は無料です。一般的な他社の場合は、一般的な売却はもとより、買取業者に売る場合でも売買価格の3%が基本のようですね。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下の金額 | 売却価格 × 5.5% |
| 200万円を超えて400万円以下の金額 | 売却価格 × 4.4% |
| 400万円を超える金額 | 売却価格 × 3.3% |
宅建業法の一部改正により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料は、「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」を適用し上限を18万円までとすることが可能です。この上限を適用する場合は、媒介契約時に売主と合意する必要があります。

自主売却が事実上難しいので、3%かどうかは別として、売却にあたり手数料を経費とするのは、止むを得ないと言えるでしょう。
印紙代
契約書には売買価格が記載されますので印紙を貼付して印紙税の実費をご負担いただきます。高額の収入印紙は郵便局などで買い求めることができます。当社へ売却をご依頼いただければ、準備をしておきます。
買主様のローンがある場合は、ローンキャンセルによる白紙解約があるため、売却の場合はご決済時に貼付することがいいかもしれません。当社ではそのようにお勧めしています。
| 売買契約書に記載された価格の区分 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超、1,000万円以下 | 5千円 |
| 1,000万円超、 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超、1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超、5億円以下 | 6万円 |
- 500万円以下、並びに5億円以下の価格区分は割愛しました。
- 上記の価格区分は平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される契約書について該当します。
- 詳細は国税庁のタックスアンサーの「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」もご確認ください。
状況によりかかる経費
経費の中には物件の置かれている状況によりかかるものもあります。

一括繰り上げ返済の手数料
抵当権の設定がある場合、売却では金融機関が発行する抵当権の解除の証書が必要となります。
一般的な繰り上げ返済では、オンラインで一部繰り上げ返済をするには手数料は無料なのですが、売却でローンを完済するには、最後に抹消書類を受け取る必要があるため、店頭での完済が必須です。
店頭での完済の場合には、多くの銀行では手数料を要求するようになっています。2~5万円が相場のようです。
抵当権の抹消
登記簿上に住宅ローン等の抵当権がある場合は、引渡しの前に抵当権の抹消の準備を行います。
件数や司法書士の手数料により金額が変化します。報酬は1.5万~3万円くらいが相場のようです。登録免許税は不動産1件(土地と建物は別々。土地も筆が分かれれば別々)につき1,000円です。残債がなければ、お時間と心得があればご自身でも可能だと思います。
住所変更・氏名変更の登記
登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住所の実態に合わせて、登記を変更します。
こちらも報酬は1.5万~3万円くらいが相場のようです。登録免許税は不動産1件につき1,000円です。お時間と心得があればご自身でもできるかもしれません。
相談により判断すべき費用
買取業者に売る場合はプロであり、境界明示を除いて、後日、すべてリフォームされますので、すので、かようなものは不要です。
境界明示・測量(土地・戸建て)
土地を売却では、しばしばお隣さんの土地との境界が不明瞭な場合があります。境界が不明瞭な場合には境界の明示や測量を求められることが多いようです(交渉途中での条件による)。
土地の形状により費用が異なりますので、具体的な見積もりが必要です。
建物現況調査費用
「雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐朽・腐食、給排水管の故障」は、一般的な不動産売買契約約款において瑕疵とされます。その要因事象の有無を、既存住宅状況調査技術者が調査を行い、報告書を作成します。
欠陥の有無を可視化できますので、売却のときの安心感を提供できます。
リフォーム費用・クリーニング費用
空室で売却を行う場合、著しく状態が劣化した場合は、リフォームをすることで好印象となり、販売が有利になる場合があります。リフォームをするまでもない場合でも、クリーニングをすることで好印象となる場合があります。5万~10万くらいでしょう。
ホームステージング
販売の好印象度を高めるため、少し綺麗な家具やカーテンを設置することがあります。最も極端なホームステージングの例が新築マンションのモデルルームです。モデルルームのような華美なデザインは不要ですが、お花やカーテンなどがあれば、きれいに見えますね。
空室のお部屋の売却受託では、花を添える程度のサービスであれば、売りやすくするための措置として、当社では自主的・無償で行っています。

解体費用(土地・戸建て)
古家がある土地の場合、解体が契約条件になる場合があります。著しく古い建物の場合は更地にすることで販売が有利になる場合があります。施工環境により費用が異なりますので、具体的な見積もりが必要です。
広告費の負担はありますか?
不動産業者を通して住宅を売却をしようとする場合、ご所有の物件情報を広告することになりますが、お客様に広告費を請求することはございません。共同仲介の協力業者に対する支払いもありません。
不動産売却時にかかる税金
不動産を売却すると、仲介手数料や印紙代といった費用だけでなく、「税金」がかかるケースもあります。売却後に「思ったより手元に残らない」とならないよう、税金の仕組みも押さえておきましょう。
法人売主が建物を売る場合の消費税などもありますが、このページでは特に譲渡所得税について詳しくご説明します。
譲渡所得税とは?【利益が出たときだけ課税】
譲渡所得税は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。利益が出れば、保有期間の長期と短期で税額が変わります。
利益が出なかった(譲渡所得がゼロまたはマイナス)の場合は、課税される所得がないため原則は申告不要ですが、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などを使いたい場合には申告が必要です。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
ただし、居住用財産なら3,000万円特別控除が適用され、大きく節税できる場合もあります。(後述)
取得費とは?
取得費とは、物件の購入価格に加え、購入時の仲介手数料や登記費用などを合計したものです。ただし、建物部分については減価償却によって価値を減額して取得費に組み込みます。
取得費に含めることができるもの一覧
- 購入代金(売買代金)
- 仲介手数料(購入時に不動産会社へ支払った手数料)
- 登記費用(登録免許税・司法書士報酬など)
- 売買契約書に貼付した印紙代
- 不動産取得税(購入後に支払った税金)
- 土地・建物の測量費用(境界確定測量費など)
- 土地の造成・改良工事費用(地盤改良・整地など)
- 建物のリフォーム費用・増改築費用(資産価値を増す工事)
- 古家解体費用(土地取得を目的とした場合)
- 建物の設計費・建築確認申請費(新築時)
譲渡費用とは?
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった費用を指します。譲渡所得を計算する際、売却価格から差し引くことができ、結果として課税額を減らす効果があります。
【譲渡費用に含められるもの】
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書に貼付した印紙代(売却時)
- 建物の取り壊し費用(売却条件として解体した場合)
- 測量費用(土地売却のために必要だったもの)
- 売却活動にかかった広告費(特別な掲載や広報を行った場合)
- 境界確定費用(土地売却に必要な場合)
- 売却時に支払った司法書士報酬(登記手続きに関連するもの)
- その他、売却に必要不可欠だった費用
【注意】取得費と譲渡費用の違い
取得費は「買ったときにかかった費用」、譲渡費用は「売ったときにかかった費用」です。混同しないように整理しましょう。
- 購入時の仲介手数料 → 取得費に含まれる
- 売却時の仲介手数料 → 譲渡費用に含まれる
減価償却に注意
建物部分は、以下の式で減価償却を計算します。なお、建物価格の90%が償却対象となります。1年未満でも1年としてカウントします。
減価償却累計額 = 建物価格 × 90% × 償却率 × 経過年数
償却率は建物構造によって異なります。なお、建物の構造別の耐用年数を一覧で示すと以下の通りです。
【事業用の場合】
「事業用」で使用していた建物は、たとえばRC造(鉄筋コンクリート造)の事業用耐用年数は47年ですが、事業用のRC造の建物の償却率は、1÷47= 0.22です。
| 建物の構造 | 耐用年数(事業用) |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造(住宅用) | 22年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材3mm超〜4mm以下) | 27年 |
| 重量鉄骨造(骨格材4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 |
| 石造・れんが造・ブロック造 | 38年 |
【非事業用(自宅など)の場合】
自宅など「非事業用」で使用していた建物は、事業用耐用年数の1.5倍をもとに償却率を決めます。たとえば、RC造(鉄筋コンクリート造)の事業用耐用年数は47年ですが、非事業用なら、47年 × 1.5 = 70.5年(小数点以下切り捨てで70年)です。
つまり、事業用のRC造の建物の償却率は、1÷70= 0.15と計算します。
| 建物の構造 | 耐用年数(非事業用) |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 33年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材3mm以下) | 28年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材3mm超〜4mm以下) | 40年 |
| 重量鉄骨造(骨格材4mm超) | 51年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 70年 |
| 石造・れんが造・ブロック造 | 57年 |
【具体例】
購入時の建物価格:2,000万円(うち90%が償却対象=1,800万円)
建物構造:RC造(非事業用) → 耐用年数70年(償却率約0.015)
所有年数:8年
減価償却累計額:
1,800万円 × 0.015 × 8年 = 216万円
減価償却後の建物価格:
2,000万円 − 216万円 = 1,784万円
減価償却の対象となるのは建物部分
ここまで減価償却について説明してきましたが、減価償却の対象となるのは建物部分のみです。土地は減価償却の対象となりません。実務では、建物価格と土地価格を分けないで売買することも多いので、建物価格が不明だったりすることもしばしばです。
そこで、建物価格の算出は売買契約書に土地・建物価格の明記がない場合、合理的な計算方法によって計算を行います。一般的に固定資産税評価証明書を使って按分することが多いようです。

建物価格の算出には、一般的には評価証明を用いて計算します。東京都なら都税事務所で取得できます。

固定資産税の納付書にこのような計算書があると思います。これが参考になります。
【具体例】
固定資産税評価上の「価格」が以下のような場合、評価上の価格は4,000万円です。そのうちの割合は、土地:建物 = 3:1となります。この按分をもとに、建物価格を減価償却計算に使うわけです。
- 土地:3,000万円
- 建物:1,000万円
そこで、売却価格:5,200万円だった場合、には以下のように計算されます。ここでいうと、1300万円が減価償却の対象です。
- 土地価格:5,200万円 × 3/4 = 3,900万円
- 建物価格:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
譲渡所得税の税率は?【長期か短期かで違う】
譲渡所得税は、売却した不動産の所有期間によって税率が変わります。
- 5年超所有(長期譲渡所得):所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(所得税×2.1%)
- 5年以下所有(短期譲渡所得):所得税30%+住民税9%+復興特別所得税(所得税×2.1%)
【具体例】
譲渡所得:1,000万円の場合
- 5年超所有(長期)なら:
- 所得税:1,000万円 × 15%=150万円
- 住民税:1,000万円 × 5%=50万円
- 復興特別所得税:150万円 × 2.1%=3.15万円
- → 合計:約203万円
- 5年以下所有(短期)なら:
- 所得税:1,000万円 × 30%=300万円
- 住民税:1,000万円 × 9%=90万円
- 復興特別所得税:300万円 × 2.1%=6.3万円
- → 合計:約396万円
5年を境に税額が倍近く変わるため、売却時期の調整も重要なポイントです。
譲渡所得税がかからない・軽減される場合
以下のケースでは譲渡所得税がゼロになったり、大幅に軽減されたりします。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 売却損が出た場合
- 買い替え特例、繰り延べ特例の活用
【具体例】居住用財産の3,000万円特別控除
※「3,000万円の特別控除」は、確定申告しないと適用されません!
■ 売却価格:5,000万円
■ 取得費・譲渡費用の合計:3,150万円
譲渡所得の計算:
譲渡所得 = 5,000万円 − 3,150万円 = 1,850万円
ここに3,000万円特別控除を適用すると、
課税譲渡所得 = 1,850万円 − 3,000万円 = マイナス
→ 結果として譲渡所得税はゼロになります。
ポイント
- 居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
- 控除しきれず余った金額は繰り越しできません
- 「マイホーム売却」であること、過去2年以内に同特例を使っていないことなど、適用要件に注意が必要です
まとめ:不動産売却では税金対策も大切
不動産売却では、仲介手数料や印紙代などの目に見える費用だけでなく、「譲渡所得税」という大きな税負担が発生する可能性があります。
税金の仕組みを正しく理解し、特例控除や軽減措置を活用することで、手元に残る資金を最大化することが可能です。
ロータス不動産では、税金面にも配慮した売却サポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください!
不動産の「売る」「買う」の正しい判断をお助けするため正しい情報を提供するブログです。不動産屋の社長が2010年の創業から運営しています。
この記事の作者- 書いた人
 春日秀典
春日秀典- 資格
宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター FP 住宅ローンアドバイザー
- ご挨拶
新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。
当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。
なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。
不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。