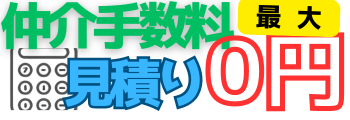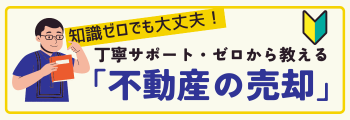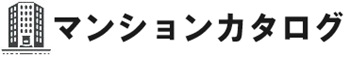売買仲介手数料の相場と手数料の値引き

売買では大手を中心に、法律の上限(3%)を仲介手数料に設定する不動産業者が多く、【手数料の相場=価格の3%】という図式です。
手数料の値引き交渉は、現実には難しく、業者が応じることはありません。私自身が社員時代に家を買った経験でも、仲介手数料の値引き交渉はできませんでした。
近年は当社のように3%という設定にとらわれない会社もありますので、ご検討できると思います。
【YouTube動画】ロータス不動産の代表こと、私、春日秀典が動画でもご説明しています。お時間がない皆様はこちらもどうぞ!
公開日: 更新日:
author:春日秀典
目次
仲介手数料の相場
仲介手数料の相場は3%
売買の場合、昭和45年の建設省の告示があります。この告知には不動産業者が請求できる報酬額の上限の記載があります。この告示によると、仲介手数料の上限額は以下の式に基づいて制限されています。不動産業者では「正規手数料」とも呼んでいます。
物件価格の3%+6万円に消費税を乗じた額
当社のような、仲介手数料を無料・半額にするタイプの不動産業者はまだ少数派ですから、大手仲介業者・有力仲介業者は依然このレートで設定をしており、おおむね、これが事実上の手数料の相場と言えます。
なお、消費税が課されている物件は本体部分をもとに計算します。
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
-
第2条 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は・・・(中略)・・・次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。>
- 二百万円以下の金額百分の五・二五
- 二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・二
- 四百万円を超える金額百分の三・一五
売買の仲介手数料の例)価格の3%+6万円+消費税なので、3000万円の物件ですと105.6万円となります。
当社のように、近頃は手数料の設定も多様化して来ていますが、以上の背景から、売買の仲介手数料の相場はおおむね「3%」とご認識いただいて結構です。仲介手数料の相場は永く宅地建物取引業法に記載されている条文と建設省の告示を根拠としてきました。不動産業者の店頭に行くと「仲介手数料は正規申し受けます」などと書いていますが、正規とは3%のことです。下記の告示がそれです。この条文が根拠となって、ながらくこの手数料の相場が定着してきました。

売却の仲介手数料の相場
日本の仲介手数料のシステムでは、売却も購入と同じレートで対応するものとされています。つまり、多くの業者では、売却の仲介手数料も3%となっています。
売却の依頼件数でいうと、まだ有名仲介業者の存在感は高いですので、売却の仲介手数料の相場は3%といって差し支えないでしょう。
たとえば当社の場合でいえば、通常の個人向けの売却(ただし税込み3%で実質1割程度の割引)だけでなく、売却の仲介手数料の無料サービスを手掛けています。売却の手数料無料はデメリットがないわけではないですし、売却はまだ有名仲介業者の存在感は高いものの、すこしづつ多様化は進んできています。

販売価格と仲介手数料
売り主に対して価格交渉の差し戻しを要求する行為
価格交渉があったとき、仲介業者の交渉動力で価格交渉を差し戻しましたとしてお、差し戻した分の分け前を仲介業者が要求する行為は違法です。そのような分を含めての3%という仲介手数料です。もしそのような提案や要求がれば、基本的にはお付き合いをすべきでない業者として対応すべきであり、お断りをすべきものと思います。
このようなことがある背景には、もともと業者さんでは両手を狙っていて、売主と買主の双方からもらう、「両手」しか容認をしない、厳しい会社だったのかもしれません。いわゆる「囲い込み」です。そのような会社が「分かれ」の取引をするようになった背景があるのだと思います。
なお、3%以上の手数料を支払うケースとしてあるのは、1)「代理」としての取引があります。これは6%を請求できるという規定があります。また、2)広告費や付加費用(交通費など)が多めにかかったなどがあります。交通費や広告費などを多く支払うのは、お客様のたっての希望があった場合の対応としては、法律でも容認されています。
仲介手数料の値引きは可能か
なにごとも、価格は当事者が決めるものですので、理論上は可能ですが、実務上は難しいと思います。とくに、物件の価格交渉ができない場合には、なお手数料の値引きができないか、考えたくなります。
物件紹介前の値引き交渉は相手にされない
いよいよ物件の決定となる段階では、仲介手数料の交渉は難しくなります。そこで仲介手数料の交渉をするとすれば、物件の紹介前にやることになります。しかし、事前に仲介手数料の交渉をするとなると、相手にされなくなります。
「少しぐらいいいだろ」と思いたいところですが、実際には応じてくれることはなく、応じた場合には、何か裏があると疑うべきレベルです。
交渉してると物件がなくなる
交渉の最終段階で、お客様が仲介手数料の交渉を持ちかけたとします。そのとき、業者は「あなたと取引しない」という判断をすることも可能ですから、その前提で交渉することになりますので、強い交渉はできません。
買わなくてもよいと考えている物件であれば、そもそも買いたくないのですから、交渉の最終段階まで到達することはないでしょう。
よしんば応じてくれる気配があったとしても、担当者はすぐには判断できません。そこで、担当者は上司に相談することになりますが、上司の判断は「理解してもらうよう交渉しなさい」の一択です。内部的にも稟議をしなくてはならず、結果は見えています。最悪、担当者は、「面倒くさいお客様とは商談を打ち切れ」というオプションを持っています。
また、仮に交渉に応じるそぶりを見せてきても、相手は会社ですので、思うような成果が得るためには2~4日のロスが生じます。ただし、実際には担当者は数字をあげたいので対応をした「フリ」をしてくれますが、担当者は右往左往しているだけで、なかなか結論が出ません。
よほどの不動産購入の経験がなければ、ここでじっくり構えているのは難しいものです。
儲かればどの物件でもよいというプロ業者の買主であれば、「手数料の交渉に応じない仲介業者からは買わない」という判断もあるかもしれません。しかし、一般個人はそれほど選択肢は広がりません。ライフスタイルにも関係するからです。また、後述のような疑心暗鬼も心配しなければなりません。
営業対応の低下への恐れ
手数料交渉を成功させたとしても、営業マンには「めんどくさい客」と思われます。一度「めんどくさい客」というレッテルを貼られると、営業マン心理としては、「言われたことだけをこなすべき客」という位置づけになります。このように人間関係の質が低下して、信頼感が低下します。心配りなどは期待できなくなるでしょう。
また、交渉を試みても、めんどくさい客と思われているかもという疑いが頭をよぎります。仲介手数料の交渉は言っては見るものの、すぐに相談を引っ込めることになります。

面倒な客と思われるのも以後の対応を考えると得策ではありません。
大手は交渉には応じない
大手仲介業者(財閥系・金融機関系・電鉄系・全国規模)の会社は、社員の統率の問題と、自らのブランドに対する自信もあり、手数料の交渉に応じることはありません。
とくに、物元となっている物件については、だれに売ってもいいわけですので、戦略的に長いお付き合いを戦略的に行うべきリピーター(資産家・買取業者・機関投資家など)以外には、大手仲介業者が手数料の値引き交渉に応じることはありません。
このため、大手が物件をグリップしている「囲い込み物件」「専任返し物件」などは、手数料の交渉は現に慎むべきといえます。

大手ほど経験があり老獪です。
当社のような手数料無料・割引サービスの業者も
「3%」とは、単に法律の上限
しかし、よく注意してみると、法律記載の3%というのは「上限」であり、「3%にすべし」書いておりません。仲介手数料は成功報酬であり、それぞれの業者が自由に設定できます。仲介手数料自体は不動産業者が業務を継続するにいただく対価で、重要な意義がありますが、金額の設定は業者の自由だったりするわけです。
https://www.fudousan.or.jp/kiso/sale/chukai.html
仲介手数料の趣旨は、もちろん仲介業務の対価です。「不動産ジャパン」の用語解説では、「法規制により仲介手数料には上限がある」「仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する」等との記入があります。
手数料割引サービスの業者も
例えば当社であれば免許番号は(3)です。すなわち10年以上、仲介手数料無料ののビジネスモデルでやっています。売却の手数料無料はほとんどありませんので、仲介手数料の値引きが難しいのであれば、最初から割引で出している業者の利用も検討できるかと思います。
当社が扱えない物件は、その旨を申し上げます。大手の囲い込み物件などの場合は、仲介手数料無料は役に立てない場合もあるからです。
弊社であれば、気になる物件の仲介手数料が無料/半額になるかの見積もりも無料で行います。奮ってお問い合わせをください。
定率が基本の仲介手数料ですが、1000万円のマンションも3000万円のマンションも、実は概ね同じような仕事です。これこそ当社のようなタイプの業態(仲介手数料が無料/半額)でも事業が成り立つというカラクリがあります。(⇒手数料無料のカラクリ)(⇒手数料半額のカラクリ)
不動産の「売る」「買う」の正しい判断をお助けするため正しい情報を提供するブログです。不動産屋の社長が2010年の創業から運営しています。
この記事の作者- 書いた人
春日秀典
- 資格
宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター FP 住宅ローンアドバイザー
- ご挨拶
新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。
当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。
なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。
不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。